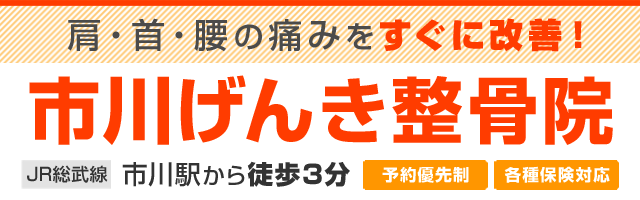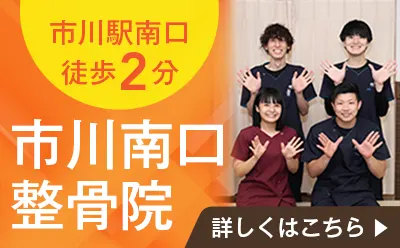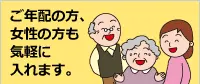巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

肩こり・首こり
猫背や姿勢の悪化
頭痛の発生
呼吸が浅くなる
肩関節の可動域の狭まりと四十肩・五十肩のリスク
腕のしびれやバストの位置の変化
肩が前に出ることで首や肩周りの筋肉が緊張しやすくなり、こりや痛みが起こりやすくなります。また、背中が丸まりやすくなるため姿勢が悪く見え、特に長時間のデスクワークではその傾向が強くなりやすいです。さらに、首や肩の筋肉の緊張により血流が悪くなり、緊張型頭痛が起こることがあり、特に頭の後ろに痛みが出やすい傾向があります。肩が内側に巻くことで胸が開きにくくなり、深い呼吸がしづらくなるため睡眠の質が低下しやすくなります。肩関節の動きが制限されやすくなることで、高い場所のものが取りにくくなるなどの不便を感じることがあり、将来的に四十肩や五十肩のリスクが高まる可能性があります。さらに、肩が前に出ることで神経が圧迫され、腕や手にしびれが出ることがあり、胸が内側に入り込むことでバストの位置が下がり、見た目にも変化が現れやすくなります。
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩とは、肩が前方に巻き込まれ、肩甲骨が外側や上方に引っ張られて前に傾いた状態を指します。この姿勢は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、日常生活で腕を前に出す動作が多いことが主な原因です。その結果、肩甲骨が外側や上方に引っ張られ、前に倒れることで巻き肩が形成されます。
巻き肩は、首から肩の筋肉の硬さや肩の可動域の制限、呼吸の浅さ、スタイルの悪化など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。また、猫背とは異なり、巻き肩は肩甲骨や肩、腕に注目した状態を指します。横から見て背骨が丸まっているのが猫背であり、上から見て肩のラインが丸まっているのが巻き肩とされています。
巻き肩の改善には、正しい姿勢の意識や筋肉のバランスを整えることが重要です。具体的には、肩甲骨を内側に寄せて胸を開く姿勢を心がけることや、腕を内旋させないように意識することが効果が期待できる方法です。また、巻き肩は左右で異なる状態で引き起こされることが多く、右肩が前に回転し、左肩がすくんだ状態になることが一般的です。これは、右利きの方が多く、デスクワークなどで利き腕が前に出る姿勢を長時間続けることが原因と考えられます。
日常生活では、同じ姿勢を長時間続けないようにし、20~30分に一度は背筋を伸ばして肩甲骨を引き寄せることが推奨されます。また、スマートフォンを使用する際は目の高さに持ち上げて、肩が前に出ないように注意することも効果が期待できる対策です。意識的な姿勢の改善や適切なエクササイズによって改善が期待できるため、日常生活での姿勢に注意を払うことが大切です。
症状の現れ方は?

主な症状としては、首から肩にかけての筋肉の硬さや重さ、だるさや痛み、頭痛、猫背、呼吸の浅さ、腕のしびれなどが挙げられます。これらの症状は、巻き肩によって肩甲骨や周囲の筋肉のバランスが崩れることで引き起こされることが多いです。特にデスクワークやスマートフォンの長時間使用など、前かがみの姿勢を続けることで、胸の筋肉や首の前の筋肉が硬くなり、巻き肩の症状が悪化しやすくなります。また、そこから出ている神経に圧迫がかかると、腕全体のだるさやしびれが生じることもあります。日常生活での姿勢や動作に注意を払い、適切なストレッチやエクササイズを取り入れることで、巻き肩の症状の予防や改善が期待できます。
その他の原因は?

一番の原因は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、前かがみの姿勢を続けることです。座ったときに頬杖をついたり肘をついて長時間同じ姿勢をとり続けることで、胸の前側の筋肉(大胸筋や小胸筋)が硬くなり、肩を内側に引っ張ります。さらに、運動不足や筋力低下も巻き肩の一因となります。特に肩甲骨を支える筋肉(僧帽筋など)の弱化は、正しい姿勢の維持を困難にします。また、横向きで寝る習慣も下側の肩に負担をかけ、巻き肩を引き起こす可能性があります。これらの要因が組み合わさることで、肩が前方に巻き込まれ、巻き肩の状態が形成されると考えられます。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、さまざまな健康問題が生じる可能性があります。まず、肩甲骨や首の筋肉が緊張しやすくなり、肩こりや首こりによる痛みや疲労感が増加します。また、首や肩の筋肉が硬直すると脳への血流が滞り、緊張型頭痛やめまいが生じることがあります。さらに、胸郭が圧迫されることで呼吸が浅くなり、肺活量が低下します。これにより体内の酸素供給が不足し、疲労感や集中力の低下が引き起こされることもあります。加えて、猫背姿勢を伴う巻き肩では胃や腸が圧迫され、消化不良や便秘などの内臓不調を招く可能性があります。加えて、姿勢の悪化は見た目の印象に影響を与え、自信の喪失や精神的なストレスを引き起こすこともあります。
当院の施術方法について

1.筋肉に対するアプローチです。肩周りの硬くなった筋肉を緩めるために手技施術やストレッチを行い、症状が強い場合には鍼施術もおすすめしております。また、筋肉量を増やすためにEMSなどの電気療法を取り入れることもございます。
2.骨格に対するアプローチです。筋肉を緩めただけでは日常生活の負担により再び同じ状態に戻ってしまうことがあるため、骨格からのアプローチも推奨しております。具体的には、巻き肩の原因は肩関節が内側に入ってしまい、それに伴って肩甲骨が外側に開いてバランスを取るために背骨の位置が悪くなることにあります。そこで、矯正施術により骨格を正しい位置に戻すことを行っております。
改善していく上でのポイント

巻き肩の症状を改善するためには、以下のポイントに注意することが効果が期待できるとされています。
1.姿勢の見直しが重要です。日常生活で背筋を伸ばし、肩甲骨を引き寄せるように意識しましょう。特にデスクワークやスマートフォンの使用時には、前かがみの姿勢を避けることが大切です。
2.ストレッチとエクササイズを取り入れることをおすすめします。胸の筋肉(大胸筋や小胸筋)のストレッチや、肩甲骨周りの筋肉(僧帽筋や菱形筋)を強化するエクササイズは、筋肉のバランスを整え、巻き肩の症状の改善に役立ちます。
3.生活習慣の見直しも必要です。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は巻き肩の原因となりますので、作業中は定期的に休憩を取り、姿勢をリセットすることが重要です。さらに、睡眠時の姿勢も影響しますので、仰向けで寝る習慣をつけることをおすすめします。
4,症状が強い場合や自己ケアで症状の改善が期待できない場合は、整骨院などの専門家に相談することをおすすめします。専門的なアドバイスや施術を受けることで、症状の改善が期待できます。
監修

市川げんき整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:千葉県市川市
趣味・特技:居酒屋巡り、アウトドア